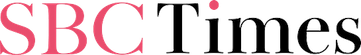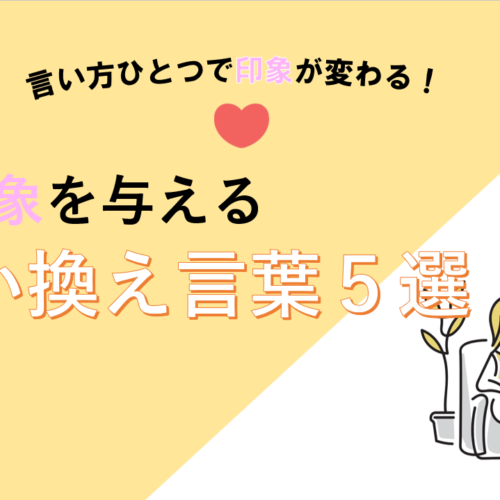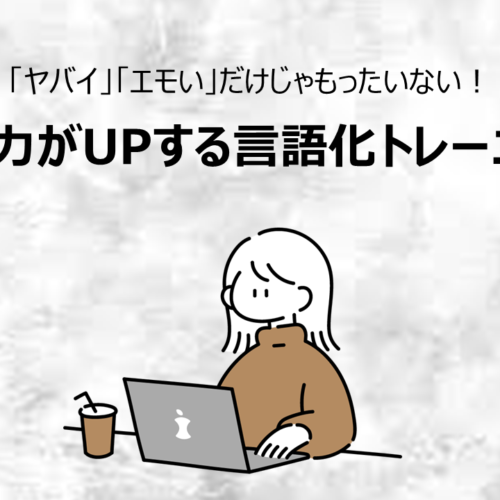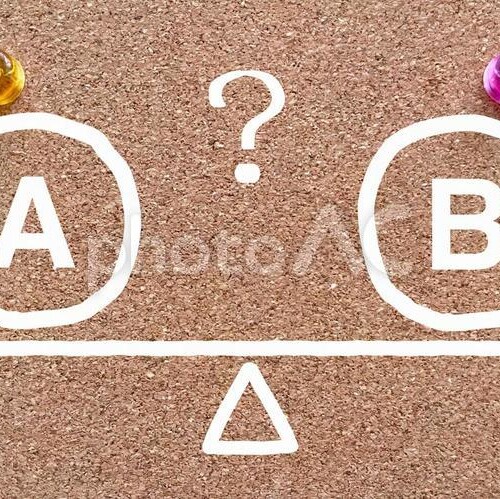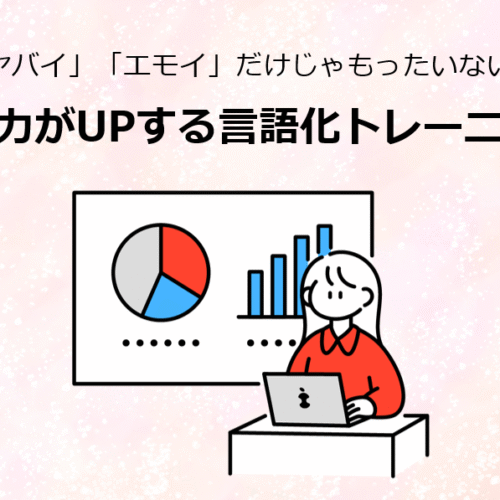部下が自ら考え、動き出す!教える➡引き出す へのコミュニケーション術
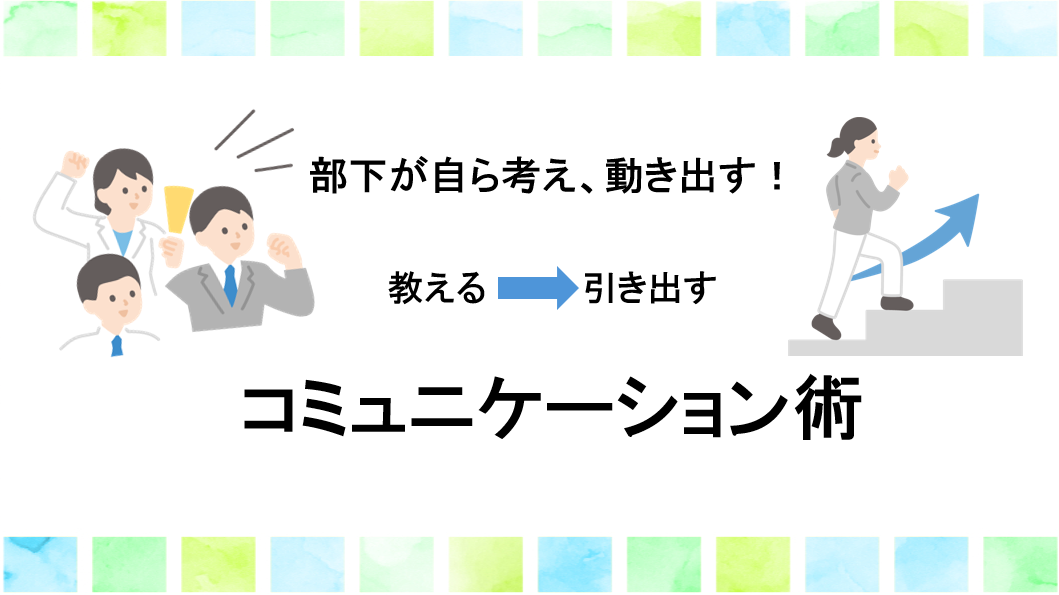
🤨「意欲が見えにくいスタッフへの最適な接し方は?」
🙄「若手の主体性をどう育めばいい?」
😥「褒める文化の中で、どうやって注意すればいいんだろう…?」
後輩や部下と関わる中で、誰しも一度は悩んだり考えた経験があるのではないでしょうか?
教育施策でアンケートを取ると必ずといっていいほど寄せられるのが<後輩や部下との関わりについて>。
寄せられるコメントから、スタッフ一人ひとりと真剣に向き合い、どうにか成長を後押ししたい!という想いが伝わってきます。
育成に悩みはつきものです。
そしてその悩みは、決してあなた一人だけが抱えているものではありません。
今回の記事ではあるある悩み・3つに焦点を当て、今日から少し試してみたくなるような関わり方のヒントを、具体的な会話例と共にご紹介します♪
ヒント1:【若手の主体性を引き出し、成長を加速させる関わり方】
「手取り足取り教えるべきか、それとも少し突き放して見守るべきか…」
特に新卒や若手スタッフに対して、このジレンマを感じる人は多いのではないでしょうか。
私たちが良かれと思って先回りしすぎると、相手は「指示待ち」の状態になってしまうことがあります。
主体性は「与える」ものではなく「引き出す」もの。
そのための3つのポイントをご紹介します。
①「Why(なぜ)」から伝える
私たちはつい、忙しさから「What(何を)」と「How(どうやって)」だけを伝えてしまいがちです。
しかし、人はその仕事の目的や背景(Why)が分かると、工夫しようと考え始めます。
【会話例】
NG例 : 「このアンケート、明日までに入力しておいてください」
OK例 : 「今度のチーム施策、お客様の声をしっかり反映させたくて。そのために、(Why) このアンケート結果がすごく重要なんだよね。(What) 明日までにデータを入力してもらえるかな? (How) 何か分からないことがあったら、いつでも聞いてね」
②「小さな成功体験」を積ませる
いきなり大きな壁を登らせるのではなく、少し頑張れば手が届く「小さな段差」を用意してあげましょう。
「できた!」という実感の積み重ねが自信となり、「次もやってみよう」という意欲につながります。
③ 答えを渡さず「質問」で返す
すぐに答えを教えるのは簡単ですが、ぐっとこらえて質問で返してみましょう。
自分で考え、出した結論だからこそ、その行動に責任感が生まれます。
【会話例】
部下: 「この件、どう対応したらいいでしょうか?」
あなた: 「確かに対応に困るよね。どうしようか?〇〇さんなら、まずどうするのが良いと思う?」 「うんうん、その方法いいね。他にはどんな選択肢がありそうかな?」
ヒント2:【モチベーションが見えにくいスタッフの心に火をつける関わり方】
「あの子は、何を考えているんだろう」「やる気、あるのかな…?」 そう感じてしまうスタッフもいるかもしれません。
しかし、もしかしたらエネルギーの向け方が分からなかったり、自分の役割に自信が持てなかったりするだけかもしれません。
そんなスタッフの心を温める関わり方です。
①「承認」のシャワー
「褒める」は特別な成果に対して使われがちですが、「承認」は、相手の存在や日々のプロセスそのものを認めることです。
(褒めるについては こちらの記事 でも紹介しています♪)
当たり前に思えることこそ、言葉にして伝えてみましょう。
【声かけ例】
「〇〇さんがいてくれると、チームの雰囲気が本当に明るくなるよ。いつもありがとう」
「いつもミスがなくて丁寧だね。当たり前のようで、実はすごいことだよ!助かっています」
② 相手の「興味のありか」を探る
1on1などの面談で、少しだけ仕事のことから離れて、相手が大切にしている価値観や興味があることに耳を傾けてみましょう。
その人の「好き」や「得意」が分かれば、仕事との思わぬ接点が見つかることがあります。
③「期待」を具体的に伝える
「もっと頑張って」という漠然とした言葉は、相手を追い詰めてしまうことがあります。
そうではなく、「あなたにこうなってほしい」という具体的な期待を伝えることで、相手は進むべき方向が明確になります。
【会話例】
NG例 : 「最近、調子悪いんじゃない?○○さんらしくないね。もっと頑張ってよ」
OK例 : 「〇〇さんの強みは、誰よりも丁寧にお客様と向き合えることだと思う。だから、今度のMTGで、その『お客様との向き合い方』について少し話をしてくれないかな?みんなの良いお手本になるはずだよ」
ヒント3:【「褒める文化」だからこそ響く、ポジティブな指摘の伝え方】
「こんなことを言ったら、パワハラだと思われるかも…」「関係性が悪くなったらどうしよう…」 注意や指摘をすることに、恐怖心やためらいを感じる方も少なくないでしょう。
大切なのは、相手の「人格」ではなく、改善可能な「行動」に焦点を当てること。
そして、それは「あなたへの期待の表れ」だと伝えることです。
①「You(あなた)」ではなく「I(私)」を主語にする
「You(あなた)」を主語にすると、相手は責められているように感じてしまいます。
「I(私)」を主語にして、自分の気持ちとして伝えることで、相手は受け入れやすくなります。
【会話例】
NG例 : 「どうして報告がいつも遅いの?(あなたが悪い)」
OK例 : 「報告を早めにくれると、私(I) が次の判断をしやすくなって、とても助かるんだ」
②「サンドイッチ話法」を活用する
伝えにくい本題を、ポジティブな言葉で挟むテクニックです。
クッション言葉があることで、心の負担が和らぎます。
【会話例】
(褒める) 「いつも■■の作業、ありがとう。早いから助かっているよ」
(指摘・要望) 「もし可能なら、■■の作業の時に▲▲まで一緒に確認して報告してくれると、私が全体を把握しやすくて更に嬉しいな」
(期待) 「〇〇さんはいつも丁寧だから、報連相がしっかりできるようになるともっと良くなると思うよ。期待しているね」
おわりに
いかがでしたか?
育成にたった一つの「正解」はありません。
今回紹介したヒントも、相手や状況によって効果は様々だと思います😌🌱
大切なのは、完璧な指導者を目指すことではなく、「どうすればこの人の力がもっと引き出せるだろう?」と考えることをやめない姿勢そのものなのかもしれません。
指導方法に困ることや、こんな時どうしたらいいんだろう?と悩むことがあれば、上長や教育部をいつでも頼ってくださいね⭐